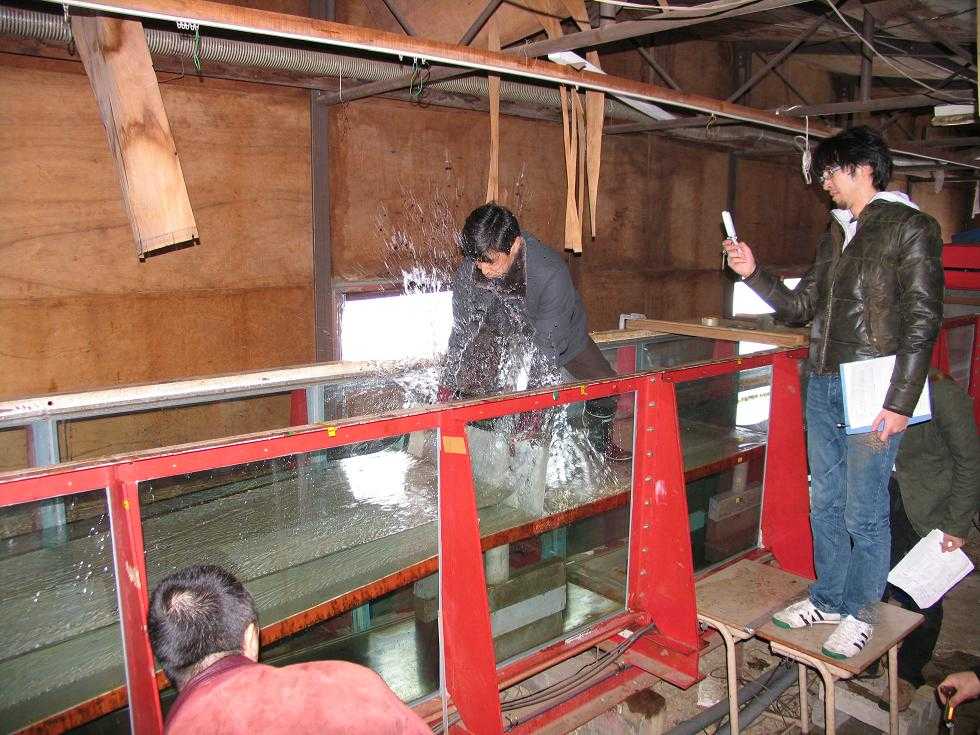工学系技術室 千葉 寿 技術専門職員の共著論文が、2011年4月10日に、
英国科学雑誌「Nature Physics」のオンライン速報版にて公開されました。
掲載情報は以下の通りです。
論文タイトル:”Strong-Laser-Induced Quantum Interference” (高強度レーザー誘起量子干渉)
著者:Haruka Goto, Hiroyuki Katsuki, Heide Ibrahim, Hisashi Chiba, Kenji Ohmori
掲載誌:Nature Physics
掲載日:Published online: 10 April 2011 | doi:10.1038/nphys1960
http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/full/nphys1960.html
本研究は、自然科学研究機構分子科学研究所・大森グループ(大森賢治教授)を拠点に行われました。
研究の概要は、下記URLからご覧下さい。
http://www.ims.ac.jp/topics/2011/110411.html
また、本情報は、岩手大学HPにも掲載されました。
http://www.iwate-u.ac.jp/news/news201104.shtml#955