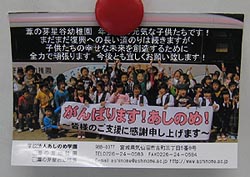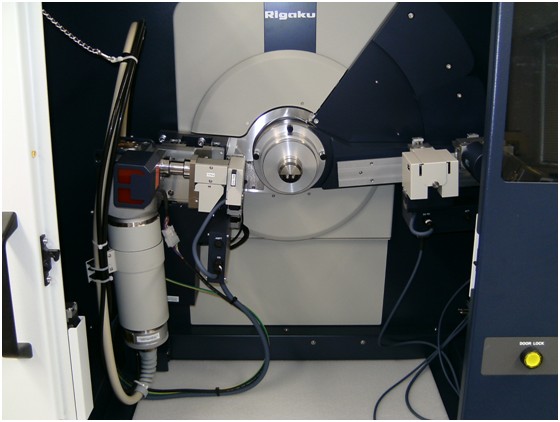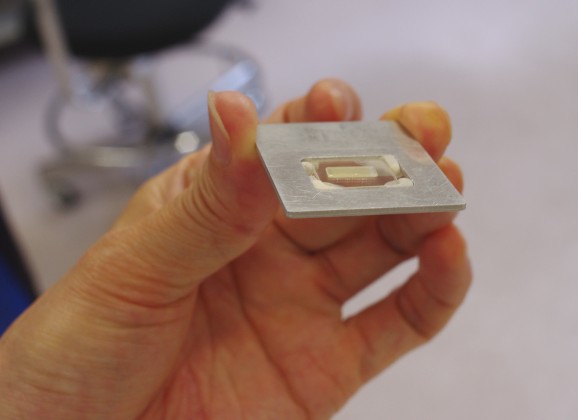改めて、復興PC班の作業内容を、紹介させていただきます。
まず、送られてきたパソコン等は、薬品管理室で受け付けます。
薬品管理室は工学部1号館の玄関の直ぐ脇にあることから、ここで受付をお願いしています。

ま、ここのチーフも技術職員ですから。
荷物を受け取ると、技術室に連絡が行き、手の空いているスタッフが台車で作業場所まで運びます。
ここが作業場所の教育研究共用棟。

この中に防災センターと工学系技術室があります。
荷物が多い場合は、運送屋さんには直接こちらに降ろしていただくよう、お願いしてあります。
運ばれた荷物は、最初に情報管理班が、受け入れリストを作ります。

受け入れデスクです。
散らかっていますね・・・
ここでPCの動作確認と、スペックの確認を行っています。
OSはWindowsXPsp3としていますので、メモリが不足している場合は、最低でも512MBに増設します。
ノートにはマウスも付け加えることもあります。
送っていただいた方に、受取確認を兼ねて、礼状を送っています。
受け入れが終わると、整備作業の待ち行列にパソコンを置きます。
次はWindows班の作業になります。
プリンタやスキャナ、ネットワーク関係等はサプライ班にまわります。
パソコンの初期化、OSやその他アプリのインストール、アップデート作業は、一台一台行います。
同じ機種については、1台のみインストール作業をし、ハードディスクを外します。

インストールしたハードディスクをマスター・ディスクとして、コピーツールでどんどんコピーを行います。

コピーが終わったハードディスクから本体に戻し、一台一台パソコンの名前を書き換えます。
『IU-xxx』という名前にしています。
xxxは管理上の番号で、一台ごとに違えてあります。
整備が終わったら、整備担当者以外のWindows班のメンバにより、作業内容に漏れがないかを確認し、管理台帳に管理番号とMACアドレスを記録します。
作業がすべて終わったら、”お化粧”コーナーに持って行きます。

このコーナーでは、ある程度溜まってくると、手の空いているスタッフが、おもむろに作業を始めます。

コンプレッサーでキーボードの隙間に入っているゴミや埃、カスを吹き飛ばします。
デスクトップは中を開けて、やはり埃を吹き飛ばします。
その後、パソコンの本体とディスプレイをクリーナーで拭きます。
キートップも、できるだけ一つ一つ拭いています。
これが終わったら、完了済み行列に並べます。

デスクトップの場合は、本体のみだったり、同一機種を複数台送っていただいたケースがあります。
そういったパソコンについては、この段階で、ディスプレイ、キーボード、マウスを組み合わせて動作を確認します。

その後、付属品のあるものにつては付属品も揃えて、セットを完了させます。

可能なものは、この段階で梱包してしまいます。

デスクトップは箱詰めにして保管しています。

ノートパソコンは、一つの箱に複数台詰められるので、注文が来てから梱包します。
それまでは、プラスチック・コンテナに入れています。

同じ機種が多いと、こんな感じになります。
プリンタも同様に梱包して保管しています。

梱包といっても、行き先が決まった段階で入れる書類があるので、封はまだしません。
いよいよ依頼が来ますと、必要台数を揃えて、運送屋さんに連絡します。
運送屋さんは、私たちがパソコンを保管している部屋まで、取りに来てくれます。

以上、こんな感じで、作業してます。